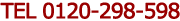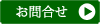ぼやき店長です!
さて、冒頭の「明和7年」ですが、
明和と聞いて、明治の明に昭和の和が入っていますので
誤字じゃないかと思った方ほとんどだと思います
もし、「ああ、明和ね」と、つぶやいた方は、相当な江戸マニアです
そうなんです
明和7年というのは江戸時代の元号で、西暦でいうと1770年です
数年前、この、1970年に建てられた、土蔵をリフォームさせてもらったことがあります
ある地方の旧道沿いに面した農家の方でした
広い敷地に12坪ほどの土蔵がぼつりと建っていました

江戸から代々続く農家の方で私には、その価値がわかりませんでしたが、
施主様は先祖様からの引継ぎを守るべく、改修にふみきられました
お話を伺うと、生まれてから、一回も中に入った事がないとの事
屋根壁が朽ち、(土で出来ています)ボロボロでしたので、新築当時に戻して欲しいとの事でした
ですが、土壁を施工する職人がおらず、相談の結果、今の土壁をこぼれないように
覆い隠すという工法で、ご了承をいただきました
実はその時、施主様もこの土蔵がいつ建てられたのが存じませんでした
ただ、うん百年前とわかっていたようです
いざ、工事が始まり、中に入ると、ほこりの山、確かに人が入った形跡はなく、
あちらこちら、時の蓄積を感じさせられるものでした
工事自体は特に難しい事はないのですが、如何せん大変なのは、中の収蔵物の保護でした
中階段があり、といってもはしごですが、登ってみると、そこにも収蔵物が山のようにありました
照明をたよりに、あちこち探ると、なにやら、天井の一番高い所に、一枚の古い板がありました
どうやら、上棟時に埋没された、棟板のようです
棟板というのは、建築年と棟梁の名前が記されたのもです
おやっと思い、目を皿のようにしてみると、「明和7年〇〇兵衛(多分大工さんの名前)」

この発見を施主様に伝えると、施主様は驚き半分、感慨半分のご表情でした
後日、収蔵物を専門家に価値があるか、鑑定してもらったようです
工事が先に終わったので、その鑑定結果は教えてもらえませんでしたが、
ひょっとしたら大化けしているかもしれませんね
(#^.^#)