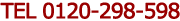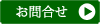店長ぼやきます!記000141 5月2日「どこから?」
2025年05月02日
ぼやき店長です!
さて、冒頭の「どこから?」ですが、
その昔、何かの漫画で、雨が降ると天井から雫がたれ、洗面器を置いているという光景がありました
又、実際に、雨が降ると、タライとか、バケツを置き、漏水を受けている家庭がありました
雨漏り=ぼろやの代名詞です

現代の住宅では、雨漏りは大分消滅しました、ですが、時たま、漏水の相談を受けることがあります
漏水する場所は多岐にわたります
皆様は、想像されるのは、どこでしょうか?
おそらく天井が一番多いと思います、次は壁ではないでしょうか?
この漏水ですが、原因は様々です、というのも、時と事象に因るからです
例えば、風邪がビュービューふっている時に雨が漏る、

又、その風も北向きの時、もしくは、南向きの時等、
又、雨量により雨が漏ったり漏らなかったりと様々です
当然、雨が降ることから始まります
その雨が、何かの原因で、住宅の内部に潜り込み、表に出ることができずに、天井なり壁に染み出るのです
大方の雨漏りは、水の道筋を想定できますが、10軒に2軒は、この水の侵入経路が分からない事があります
イメージ的には「あみだくじ」みたいなものでしょうか

真下に落ちずにある時は右、ある時は左と道を変えていくからです
たいてい、こういう系の場合は、家の作りが非常に複雑です
一般的に、住人の方は雨が漏った場所の真上を疑います
ですが、この2、3割に当てはまった場合は漏水を止めるのは、至難の業となります
よく広告で「雨漏り110番」の広告がありますが、本当に一発で、止められるのかな?とやや勘ぐっています
一度、弟子入りしてみたいと思います
(#^.^#)
店長ぼやきます!記000140 5月1日「ももくり3年」
2025年05月01日
ぼやき店長です!
さて、冒頭の「ももくり3年」ですが、
ことわざで「桃栗三年柿八年」という言葉があります

これは、「一人前になるまで辛抱しなさい」という教えを説いた、ことわざだと思います
まあ、ざっくりですが、桃も栗も実がつくまで3~4年かかります
柿は更に長く、7~8年はかかります
ところで、住宅建設職人は、この修行期間は何年ぐらいだと思いますか?
昭和のその昔、いわゆる大工さんが棟梁と呼ばれていた時代がありました
このころの棟梁は現場を仕切る、大ボスであり、近所の方はこの棟梁に家の新築を頼んだものです

当然、大ボスになる棟梁になるには、長い長い修行年月が必要でした
専門用語ですが、「墨付け」という言葉があります
これは、家を上棟した時に凸凹をつける事を言います
簡単に述べましたが、家の構造をくまなく知らないと、出来る仕事ではありません
簡単に言えば、墨付けが出来れば、棟梁になれるという事です
この墨付けが出来るようになるまでに、長い長い下積みを先輩に揉まれながら、昔の職人は一人前になっていきました
おそらく、15年、20年はかかるはずです
翻って、令和の現代、職人さんの修行年数は、どれくらいだと思いますか?
職種により、ばらつきがあるのは仕方ない事ですが、比較しやすい、大工さんでいいますと、
今の大工さんの修行は、長くても桃と栗と一緒で3年です、早ければ、1年です
そんなに早く技術を習得できるのかと、疑問に思う方がいらっしゃると思いますが
時代の変化により、機械化、オートメーション化、デジタル化が後押しし、
昔人間が担っていた修行をコンピュータのクリック一つで、できるようになりました

良くも悪くも、修行年数の短縮化が進んでいます
40過ぎですと体力的に厳しいですが、30代前半でしたら、大工デビューは間に合いますよ
いかがですか
(#^.^#)